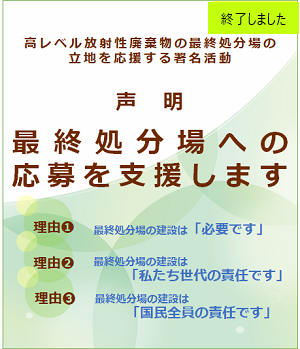原子力社会現象における「空気と水」-絶対安全と社会通念-
 宮 健三
宮 健三
原子力国民会議代表理事 日本保全学会理事長
東京大学名誉教授 工学博士
1.「空気」生成の例
日本の社会では、何か重大な決定を行うとき、「空気」が形成され、それが成長し、人々の自由な言動を金縛りにし、その「空気」によって非合理的な決断がなされてきた。
その例は、太平洋戦争に突入する前、軍や政府の幹部たちはこの戦争に勝てるはずはないことを知っていながら、猛威を振るっていた「空気」に支配され、誰一人正論を主張できず、一億総玉砕何するものぞ、とばかりに負け戦に突入して行った歴史に明白である。戦後、軍幹部は「何故、負け戦と判っていながら、抵抗しなかったのか」と問われ「あの雰囲気で抵抗できるものは一人もいなかった」と答えたという。これこそ「空気」支配の代表的なものである。「空気」による決定がこの国を滅ぼしてしまった例である。太平洋戦争は米国、英国、オランダによる日本に対するエネルギー禁輸が直接的原因であるといってよい。当時の社会状況を調べてみると、
『エネルギーが絶えると国がどんな悲惨な状況に陥るか』、
よく分かる。自暴自棄的に戦争に向かっていく以外選択肢がなかった当時の悲惨な日本。結果的に300万人が死んだ。
それ故、戦後、日本国民は大きな反省を行い、必死に復興目指して、70年間平和国家として繁栄を謳歌してきた。しかし、現在(2017/2)、米国新大統領のトランプ氏の一挙一動に暗示されるように再び激動し始めた国際情勢の中で、一部マスコミが作った反原発“空気”に支配され、原子力を捨てようとしている日本国民を見るとき、国家の運命が「空気」に決められるようなことは将来再び起こらないと考えてよいか、という命題が、放っておくことのできない重要な問題としてクローズアップしてきている。
問題の根源が、日本固有の伝統的集団倫理にあるとすれば、類似のことが将来起こるという懸念は否定できない。「空気」が集団の意を体して猛威を振るうことを許容する日本人の伝統的な精神構造が変化してしまったという兆しは何処にも見られないからである。反原発を誘導する“空気”にその兆候はないか、がここでの考察の対象である。
2.“空気”が生み出す原子力社会現象
“空気”の特性:
“空気”は一般にさまざまな禁句を作る。1mSv/yのレベルまで除染するなどばかげた話である、という言い草は特に福島地区では極めて重い“禁句”である。また、“空気”は科学的説明を受け付けない。ラジウム温泉の放射能は健康に良いが、原発に絡んだ放射線は忌避されるべき放射能であるという表現に対し、いくら科学的説明を試みても、納得してもらえない、というのがその例である。これらはまた、“空気”に関与する全ての人を例外なく“金縛り”にする。思考の自由が奪われることを“金縛り”と言う。空気生成の当事者であるメディアも例外ではない。例えば、メディアの前で「その程度の点検漏れは原子力安全にまったく関係ない」という常識を公式に発言しようものなら大変なことになり、個人であれば組織から追放されるまで攻撃される。このような原子力分野の際立ってユニークな状況下では、関係者は萎縮して正論を主張できない。これは一種の魔女狩りではないだろうか。言論の自由はマスコミのためだけにあるのか、と思わざるを得ない。
絶対安全と社会通念:
世界はチェルノブイリ事故を技術的にも精神的にもすでに克服し、新しいフェーズに入って原子力を着実に利用している。そこでは、福島事故も教訓という形で克服され、四百数十基の原発は安全に稼働中である。我が国はといえば、運転指し止め裁判のこともあるが、わずか3基だけしか稼動していない。
一言でいえば、我々の多くは、福島原発事故の悲惨さを臨在感的に把握し、その金縛りにあって、原発は嫌だ、という思いの虜になってしまっているのである。この雰囲気は“空気”の特性の一つである。こうなると、思考停止に陥り、原子力の可能性でさえ“禁句”となる。世界の原発推進への動きなどに対して目もくれない。状況を客観的に考えられなくなる。結果的に日本独特の異常な社会現象が生み出されているのである。これらの状況を倫理的に支えているのは悲惨さに裏付けされた“絶対安全”の要求であり、市民やマスコミの支持を得て、原子力利用の大きな障害になっている。
ちなみに、“絶対安全”とは、規制値の一億分の一の放射能漏れも許さず、原子炉はチェルノブイリ事故にも耐えなければならないという非現実的要求に根拠を与えている概念である。絶対安全に関する建設的な見方は、「それは現実には実現不可能であるが、安全性向上の目標になる」、ということを意味し、これは知っておくべき真実である。
“絶対安全”の対立概念は言わずと知れた“社会通念”である。これは、長期に渡って我々の日常生活に全く支障を及ぼさないとすれば、安心して許容できるという見方である。微量の放射能漏れがこれに相当し、トリチウム水を希釈して海水に放出している事実は長年続いているが、それが世界の人々の生活に支障をきたしているという話は聞いたことがない。「トリチーム水を薄めて海に流す行為は人間が生きていくうえで必要悪であり、支障は無視できるほど軽微である」という思いが社会通念である。「絶対安全」という概念を偏った形で主張して原子力推進を妨げるか、「社会通念」という日常の規範に基づいて原子力を平和利用するか、の価値判断は自明であるが、“空気”が論点を混乱に陥れている。
この社会通念という考え方が原子力の問題を正当に扱う上で大変重要なものであることを公式に表明したものは、平成19年10月26日に出された浜岡原子力発電所運転差止に関する判決書[2]に出てくる次のような文面である。原子炉施設に求められる安全性の項で、判決書は次のように記述している。
『ここにいう「原子炉施設の安全性」とは、起こり得る最悪の事態に対しても周辺の住民等に放射線被害を与えないなど、原子炉施設の事故等による災害発生の危険性を社会通念上無視し得る程度に小さなものに保つことを意味し、およそ抽象的に想定可能なあらゆる事態に対し安全であることまでをするものではない。』
ここに、我々は、絶対安全と社会通念との葛藤をみる。
反原発“空気”の横暴:
こうなると電気事業者はもちろん規制当局も軽微なトラブルに対して毅然とした科学的説明ができない。軽微なトラブルとは、社会通念に従えば、許容できる“落ち度”のことであるが、それさえ許されない異常判断が幅を利かし、その主張に本来なら常識的判断を行うはずの普通の人が振り回されるのである。勇気を持って反論しようものなら、「空気」がそれを開き直りと捉え、マスコミから受ける誹謗中傷はただ事でない。福島事故では人ひとり死んでいないといった高市大臣や1mSv/yは何の問題もないといった丸川大臣は公の場で涙を流して謝罪した。“空気”がこれらの発言を禁句としており、それに触れたらただでは済まない例である。この国に、この“空気”に挑戦している人たちは原子力国民会議以外にいるのだろうか。
このようなことが想定されるので、事業者は運転再開が技術的根拠もなく引き伸ばされるのを恐れ、「ごめんなさい」的対応に追われ、過剰な再発防止対策を余儀なくされてきた。これらを「原子力社会現象」と呼ぶ。このようなじめじめした状況は日本固有で世界では見られない。このようなじめじめした状況を作り出している“犯人”はどこにいるのだろうか。
「空気」が特別な状況を作り出し、人がこれに縛られればここに「あのような空気の下ではこうせざるを得なかった」と言うことが許される「状況倫理」が明白となる。そうすると、思考停止が生じ、間違った「事実」を「真実」と信じるようになり、そうなっている実態を反省する気も失せてしまう。
3.「空気」発生のメカニズム
恐れは人間の本能:
人類が厳しい自然環境の下で何百万年にわたって生存できた理由は、紛れもなく危険に対する“恐れ”を備えていたからである。人間も動物も“恐れ”を本能的に持っていたから生きながらえてくることができた。油断したため、あるいは身構えていても死の危険を避けることができなかった例は無数にあっただろうが、“恐れ”を事前に抱くことで避けられた危険はそれよりはるかに多かったであろう。その結果、危険を恐れる“本能”が確立した。原発に対する“恐れ”もこれに由来する。この恐れは、対象が何であるか、よく理解できない状況を前提とする。原発技術者は、原発の危険性と対策を知っているから、原発を恐れない。
“空気”は問題を解決しようとする:
西洋人は日本人のように“空気”に影響されない。また、個人的問題に関して“空気”は起こり得ない。何かの問題に関して、賛成か、反対かを集団で決めようとするきに、いつもとは限らないが、“空気”のお出ましとなる。“空気”が決めるといったスタイルを取る。このとき、西洋と日本とでは、集団が取る方法に差がある。それは、言語の特長に関して、日本語と英語のヘッドパラメータがそれぞれ、左向き、右向きであるのに似ている。日本の集団は物事を決めるときには、「全員一致を旨とする」が、西洋では「全員一致の議決は無効とする。」この違いは、農耕民族と狩猟民族の違いに帰せられるが、その理由は別の機会にしたい。この違いが日本には意思決定に影響を及ぼす“空気”が存在し、外国には存在しないことの理由になる。
そもそも、個人では解決困難な問題を“空気”の力を利用して、問題解決を図ろうとする狙いが“空気”の存在理由であり、そのとき、個人の責任回避は実現され、全員一致を実現する手段として“村八分”があり、事柄が情緒的であるため制御不能に陥り、大抵悲劇を招く。太平洋戦争はそうであった。反原発もその結果になる、という兆候はいくらでも指摘できるが、それは“禁句”によって排除されている。
反原発“空気”の生成:
一般人には理解しがたい原発と原発事故が絶対的に結びつき、原発は危険だという“恐れ”が臨在観的に把握され、それが結果的に国民のあいだに定着してしまう。これが原子力アレルギーと呼ばれる反原子力の「空気」である。ここで臨在観的という表現は、原発の場合、その背後に「チェルノブイリ事故」を見て、自分が実際に事故の被害を体験させられると思うことである。
最近では「もんじゅ」のナトリウム漏洩検出器の誤警報問題、ある電力におけるボヤ程度の火災(3回繰り返された)問題、などに関連して「空気」が発生しているが、それらを見ると次のような社会現象が生じていることが判る。
- まず、トラブルが発生する。それに対し、「その程度の放射能漏れはたいしたことはない」、「その程度の故障は何でもない」などといった常識を無視した報道が執拗になされる。そうして、この案件がマスコミによって、社会的事件にされるとここから“空気”に成長し始めていく。
- 次いで関係者が「空気」の「金縛り」にあってしまう。謝罪が要求され、釈明する機会は与えられない。その結果、事業者は「萎縮した言動」を示し、「ごめんなさい」的過剰な対応に終始しがちになる。一般市民は新聞に同調し、「そうだ、そうだ」となる。こうなると完全に“空気”の虜になる。
- トラブルの軽重に関する「科学的説明」を受け付けてもらえない。敢えて行うと開き直りと取られる。“空気”が力を持つと狂暴性が発揮される。
これに対し、「住民や県民や国民が原発は不安だ!不安だ!」という構図は、数百人から千人規模の地元の人が原発で安心して働いている日常と矛盾しており、後でいう「事実の隠し合い」がこの矛盾に存在理由を与えているとしか思えない。ここでは科学的根拠に基づいた説明が通用しないことは先に述べた。その実態を指摘すれば「直きこと」、即ち「矛盾の共存」を理解できない者としてみんなから糾弾される。これも「空気」による金縛りの結果である。
「空気」を説得できない科学:
物質の背後に何かが五感に触れない形で存在していると感じる。その結果、恐れを抱く。“恐れ”はいつも目の前の対象の背後に得体の知れないものとして把握される。
この“恐れ”に対して科学は非力である。それは人々に原発の安全性をいくら科学的に説明してみても人々の考えを変えることができないことに現れている。日本人にとって、心の中に相容れない“二心”、自然現象の理解とそれと相対する“心理現象”、を抱く羽目になっているのである。科学が万能なのは、自然や人工物といった実相の世界に置ける“現象の説明”においてだけである。
4.“空気”の分析手法
分析の糸口:
以上、“空気”がどのように生成され、どのような影響を及ぼすか、について検討した。これらの問題は国民が伝統的に持つ集団倫理に基づいて分析すれば説明できる。問題を解く鍵は、原子力における安全神話といわれた“絶対安全”、日本的平等主義に起因する集団の“状況倫理”と“隠し合いの倫理”といったキーワードにある。ここでは、集団倫理は主としてこの“状況倫理”と“隠し合いの倫理”からなる。
また「空気」に「水を差す」方法のよりどころは浜岡裁判の判決文に見られる「社会通念」にある。「絶対安全」という思想と「社会通念」という常識の葛藤が「水を差す」方法の本質である。これを「絶対安全」の「対立概念」として認識することはとても重要である。そうすれば、原発への“恐れ”も緩和される。
以下の分析は、原子力に対する人々の行動原理の分析に有用である。それらは、1)固定倫理と状況倫理、2)事実の隠し合いの倫理、の2つに集約される。それらを説明したい。
1)固定倫理と状況倫理
子供がパンを盗んだとする。このとき、状況倫理は、子供の貧しい家庭環境を考えれば盗みもある程度やむを得ない、という判断を可能にする。我が国では、このような情状酌量は概ね歓迎される。これが状況倫理である。
西洋の固定倫理は、盗みは子供がやっても王様がやっても悪い、といって譲らない。王様が罰せられた例は知らないが、罰せられて当然という倫理である。これが固定倫理である。固定倫理は非人間的で人間は関与できない。モーゼの十戒は人間と神との約束に基づいた“掟(おきて)”であって、人が決して変えることができない倫理である。このような掟は我々にはない。固定倫理と状況倫理の違いは、神との契約を規範とする人種と何でも神様にしてしまう多神教との違いによる。
論理をごまかしたり科学的に間違ったことを意図的に言ったりするのは、正常な倫理を持っている人から見れば、恥ずかしい行為であり、人から非難されてもおかしくないものである。ところが西洋の「固定倫理」からみると、これらは常に間違った行為とみなされるが、日本人社会では、許されない場合もあるが、許される場合も少なくない。それを読み取る能力が「KY(空気読めない)」であったりする。嘘も方便という諺もあるぐらいである。許される、許されないは状況次第である。これは、正しい、正しくないことが状況に依存するので「状況倫理」と呼ばれる。先に述べた「あの雰囲気ではああするしか仕方がなかった」という言明はまさに典型的な「状況倫理」である。このとき個人の行為は免責になる。
何故、日本人は己の「行為の結果」を「状況」のせいにするのだろうか。
そもそも、狩猟民族の場合、自由度がありすぎ、結果が平等であることに拘る状況は在りえなかった。それに反して、農耕民族の場合には、平等主義は集団を維持する原理の一つでなければならなかった。そしてこの平等主義はある個人が失敗の責任を負い村八分に会うことを避けるため確立された。そうだとすると、失敗は状況のせいにした方がよい。重大なことは「空気」に決めさせて、自分は責任から自由で安全な立場に立つようにした方が良い、となる。
良い例かどうかだが、中越沖地震(2004/10)で東京電力の柏崎・刈羽原発から漏れたわずかな放射能で日本海が汚染されてしまったといった報道の場合、そのような非常識な報道は通常許されないはずであるが、「絶対安全」を当然と思っている風土もしくは「空気」に拘束されてしまっている一般市民はそれを受け入れ、そこから発生する矛盾には鈍感となる。行為が“空気”に支配される状況は“状況倫理”そのものである。このような無責任社会体制が風評被害の原因の一つになっている。
2)「事実の隠し合い」の倫理:
“空気”には科学的要素はほとんどない。矛盾があっても、状況倫理に基づいて合意されてしまうことは良くある。禁句は、主張したいことを守るためそれを阻害する事柄を排除するので、そもそも科学的要素は含まれない。そこでは事実と異なるものも容認することが合意されるのである。これを「事実の隠し合い」という。論語にでている話でもある。
チェルノブイリ事故はいつでもかつどこにでも発生すると言ったり、六か所村の再処理施設のプールで冷却水が失われれば臨界事故になり、アジア全体が住めなくなると平気でいって一般市民の恐怖を煽ったりする言動は、バカバカしいといえばバカバカしい限りであるが、それを信じている人も少なくないのだから、ここには「事実の隠し合い」という社会現象がまかり通っている、という見方もできる。「事実の隠し合い」というのは、例えば、会社のために虚偽行為をした人が社会から罰せられるのを会社がかばう、というものである。反対派という固定集団の中にあっても、これはもちろん「事実」ではないが「真実」ではあるとはみなされる。事実は変えられないが、見方によって判断が異なることは否定できないから、その人にとっては真実ということになる。反対派の人々がこれを信じて疑わないかどうか判らないが、「事実の隠し合い」の倫理に基づいてこれを「真実」にしていることだけは確かである。事実はまぎれもない事実だから曲げようがないが、集団にとって都合が悪い事実は暗黙の内に了承されている「事実の隠し合い」という倫理に基づいて排除・黙認される。事実でなくても集団に都合がよいことは「状況倫理」などを活用して「真実」とされる。
これらの言明が未来に関することであれば、人々を不確実性の世界に誘うことができるので、露骨な「事実の隠し合い」に頼らなくて済む。反対派の言明が多く未来形「たら、れば」を取る理由はここにある。世界の原発は爆発して地球を滅ぼすであろう、という虚言は未来に関することだから、その否定も100%確実でない。
5.まとめ
我々日本人は、物事を集団で決めようとするとき、物事が新聞記事として取り上げられ、それが社会的事件に発展する場合には、“空気”が生成され、人々を拘束し、それに逆らうものがあれば、糾弾される、という状況に置かれ、そういう過程を経て、物事が決められていくことに抵抗できない。新聞はこの社会現象を活用する。その結果、個人は責任を免れ、自ら解を探すという労力は省かれ、ただ大勢に従っていればよいということになり、それに身を任せる。結果は幸せで終わる場合もあるが、太平洋戦争のように大悲劇に終わる場合もある。前者の例は、幕末時の尊皇攘夷の“空気”であったろう。
問題は現在の反原発の“空気”の結果はどうなるであろうか、ということである。“空気”を利用して国民をもてあそぶ一部新聞の傲慢に国民はどう対峙するか、であろう。
“空気”は日本独特のものがあり、西洋には見られない。その違いは、物事を「全員一致という形を取りながら」決めるか、「全員一致の議決は無効だ」とするかに依存している。余計なことだが、韓国の今の理にかなわない政治状況は、この国も“空気”によいように振り回されているように見えて仕方がない。
この凶暴化する可能性を持つ反原子力の“空気”に水を差す方法は、浜岡裁判の判決に言う「社会通念」であろう。しかし、この「社会通念」を持つのに大きく抵抗するのも“空気”である。この“空気”の克服なくして日本の原子力は正常化できるのであろうか。正常化できなければ、日本は衰退の一途を辿り、隣国の属国と化すのではないかという“恐れ”を消せない。
宮 健三 記
(2017年1月)
参考文献:
[1] 山本七平:「空気」の研究、文芸春秋、1983
[2] 浜岡原子力発電所運転差し止めに関する判決書 2007
この記事の閲覧数:717