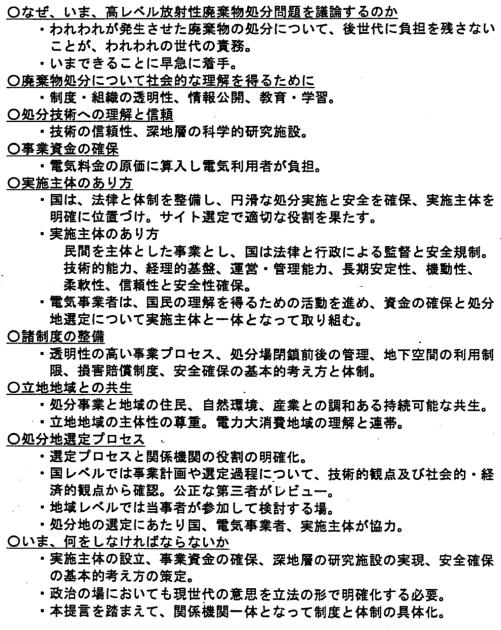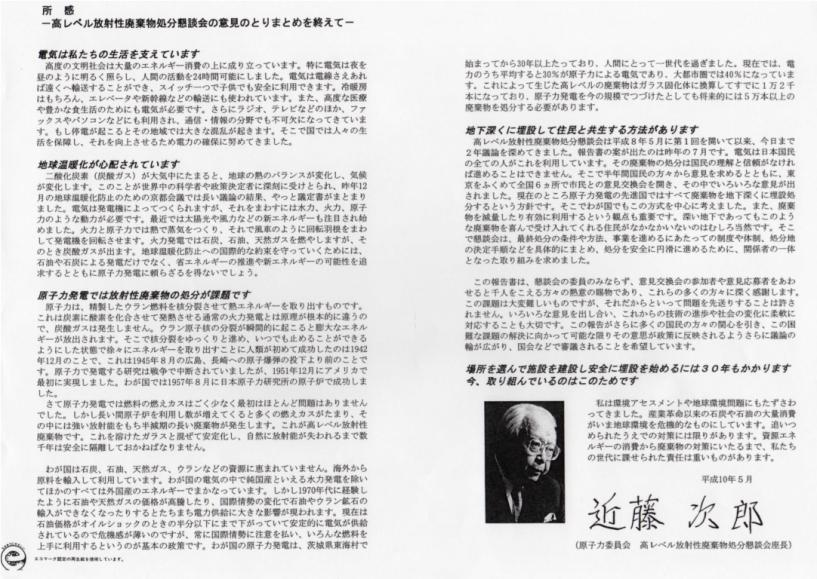「それをいつ、だれが、どこで、どのようにしてやるのか」-高レベル放射性廃棄物の最終処分について誰もが抱く疑問に、制度の面から応えようとするのが最終処分法です。処分が待ったなしになる前に技術に加えて制度についても今のうちに用意しておくことが目的です。最終処分法は、国会で圧倒的多数をもって成立し2000 年5 月に制定されました。最終処分法は、原子力発電に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処分という特定の原子力課題について、その政策を定めた画期的な法制度です。今回から最終処分の制度について、制定の背景や課題を含めて4回に分けて解説します。
地層処分技術を使うための法制度-最終処分法の制定に向けて
高レベル放射性廃棄物は長い時間、人間の生活環境から安全に隔離されなければなりません。高レベル放射性廃棄物は、原子力発電に伴って発生するのですが、熱を発するのでまず、地上の施設で地層処分に向けて「熱冷まし」をします。発生してから数十年経って、十分冷えたところで最終処分に向けて地下深部に定置します。しかし、地層処分技術が実際に社会で利用されるためには技術に加えて安心してその技術を使うための仕組み(制度)が求められ、社会が利用することを決めなければなりません。高レベル放射性廃棄物をいつ、だれが、どこで、どのようにしてやるのか?社会が抱くそのような基本的な疑問に応えるためには、技術とともに制度が用意されることが必要です。 20 世紀の終わり頃までに地層処分技術は、動力炉・核燃料開発事業団(1998年に核燃料サイクル開発機構に改組)を中心におよそ20 年の歳月を経てとりまとめられた「我が国における高レ ベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性」(いわゆる「第2次とりまとめ」、1999年)が公開され、技術的な基盤が整いました。技術基盤が用意されてきたことから、制度については、旧原子力委員会に設置された高レベル放射性廃棄物処分懇談会(処分懇)が「高レベル放射性廃棄物処分に向けた基本的考え方について」(いわゆる「処分懇報告」、1998年)として制度に取り入れるべき内容について提言として取りまとめ公表しました。
高レベル放射性廃棄物処分懇談会(処分懇)
処分懇の設置は、「国際的な専門家の検討においても、地層処分は同世代・異世代間の公平といった観点及び人間の健康や自然環境の保護といった環境面からの基本的な要請に 添うもの であり、その推進を図ることは適当である、との見解が示されている」(原子力委員会決定、1995年)との認識のもとに、地層処分技術に加えて地層処分の事業化に向けて避けて通れない処分制度の整備および社会的な理解を得るための施策について提言を受けることが目的であったと言えます。 処分懇は、設置されてから3年弱にわたる議論の結果、1998 年6 月に提言を報告書の形で取りまとめました。その間、近藤次郎座長(元日本学術会議会長)、核燃料サイクルに批判的な立場の委員などからなる調査団を編成して実施した海外調査、海外からの専門家を招聘した会合、成田空港の問題で調停役を果たされた隅谷三喜男先生を招いた会合などを挟んで本会議が14 回および社会的受容性や地域との共生について集中して検討するために設けた2つの分科会が6回ずつ開催されました。報告書案は、ドラフト段階で公表され1998年1月末までおよそ6ヶ月にわたり国民の意見を募り340名余から意見が寄せられました。意見募集と並行して公募による地域参加者を交えて6大都市において意見交換会を開催しました。なお、処分懇の設置時期は情報公開法が導入(1999年)される前でしたが、処分懇は公開で開催され、また、ドラフト段階で国民の意見を募る仕組みを導入しました。近藤次郎座長の高い指導力で進められた処分懇の審議の進め方は、当時としては画期的な試みであるとして国民やマスメディアから大きな関心を引きました。
図1は処分懇の提言を処分懇事務局が要約した内容です(http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/was te-manage/sonota/sonota12/siryo21.htm)。提言では、実施主体のあり方、事業資金の確保、処分地選定プロセスなどを制度化して現世代の意思を法律で示すことを求めています。また、提言では社会的な理解の重要性に言及していることがわかります。 処分懇の近藤次郎座長は、提言取りまとめを終えて図2のような所感を公表しています。そこでは、地層処分は、高レベル放射性廃棄物を地下深くに埋設することで住民と共生できるとしています。そのうえで、近藤次郎座長は、地球環境問題の専門家として地球環境を危機的なものにしている温暖化問題のように追い詰められた上での対策には限りがあると述べて、最終処分問題は、地層処分には場所を選んで施設を建設し安全に埋設を始めるには30年もかかるので、後世代に負担を残さぬよう自分たちの世代が今から取り組む責任があるとしています。
図2 処分懇・近藤次郎先生の所感 (http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/waste-manage/siryo/high14/siryo7.htm)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)
処分が迫られる前に今のうちに備えておくとの処分懇の提言を受けて、総合エネルギー調査会(現・総合資源エネルギー調査会)は処分事業のあり方など処分の実施方法について検討を重ね、その結果は「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(最終処分法)(2000年5月施行)の形で法制化され、地層処分の実施に向けた基本制度が整いました。最終処分法では次のように処分事業を実施する仕組みを定めています。 ① 国の基本方針(関係住民の理解の増進のための施策を含む)および最終処分計画(5年ごと、10年を一期)を通産大臣(現・経産大臣)が策定し閣議決定 ② 発電用原子炉設置者による拠出金の納付および資金管理団体の指名など処分費用の確保 ③ 処分事業(最終処分の実施、処分地の選定、施設の建設等、拠出金の徴収)に責任を持つ実施主体の設立。実施主体は民間の発意により設立される認可法人(数を定めない) ④ 「地元の意向に反して行うことはない」(大臣国会答弁)とした三段階からなる最終処分地の選定プロセス 最終処分法は、欧米諸国が処分地選定で苦しんでいるさなかに、世界に先駆けて透明性の高い処分地選定手順や発生者責任の原則のもとに安定に最終処分事業を実施するための仕組みを法 律で定めました。最終処分法では、最終処分基本方針など政策は国、事業実施主体は発生者が設立すること、発生者が処分費用を拠出することなどを定めています。法により事業実施主体として原子力発電環境整備機構が設立されました。
進まない処分地選定-「参加政策」への舵切り
これまで述べてきましたように、日本では、2000年に最終処分法を制定して処分地選定段階に入りましたが、15年以上を経た現在も進展がありません。高レベル放射性廃棄物の最終処分事業は、「人々の健康と環境の保全」と「電気を使った後始末」が関わり、併せて「将来の社会の変化にも耐えること」が求められる公益性の高い事業です。処分懇における審議で、成田空港問題の経験を参考にしたように処分地は、特定の地域を選定してトップダウン的に処分地を選定するやり方で決めることはできないと考えられました。その結果、2000年に制定された最終処分法では透明性を確保するとともに地域社会の意向に反して処分地選定プロセスを進めないことを明確にしました。しかし、民意を反映して段階的に処分地選定を実施することを明確にした最終処分法の下で国およびNUMOが最大限の努力をしても、処分地選定の第一歩である文献調査地域の選定をすることができませんでした。また、もう一つのトップダウンでもある「法律にこのように書いてあるので理解と協力を得たい」という進め方でも処分地選定は進まないことが明らかになったと言えます。 本連載の別項で述べるように、欧州各国やカナダの最終処分計画は、21世紀に入ってトップダウン型の意思決定政策を見直し「国民および地域社会が最終処分政策を信頼し、信頼をもとに処分地選定を初めとする最終処分に関わる意思決定プロセスに参加する」仕組みを導入して著しい進展を見せています。政府は、2015 年に最終処分基本方針を改定して最終処分法に定める処分地選定に先立ち最終処分について国民、地域社会の情報共有が重要であるとし、科学的特性マップを取りまとめ公表しました。政府は、科学的特性マップが最終処分について国民、地域社会が参加する対話活動で活用されること、その積み重ねが処分地選定に結びつくことを期待しています。政府は、このように「参加政策」に舵を切ったと言えますが、2018 年から国およびNUMOが本格的に取り組みだした「科学的特性マップに関する対話型全国説明会」の参加者は低迷しています。国民および地域社会が、本連載の表題のように地層処分事業を「地域発展の起爆剤」と捉えるためには、さらなる政策的な取り組みが求められます。